利用者A様の場合
Aさんは午後から週3回の通所が目標です。その為に体力増進プログラムのウォーキングは欠かさず参加しています。初めてのパソコン学習も自然と慣れてきました。
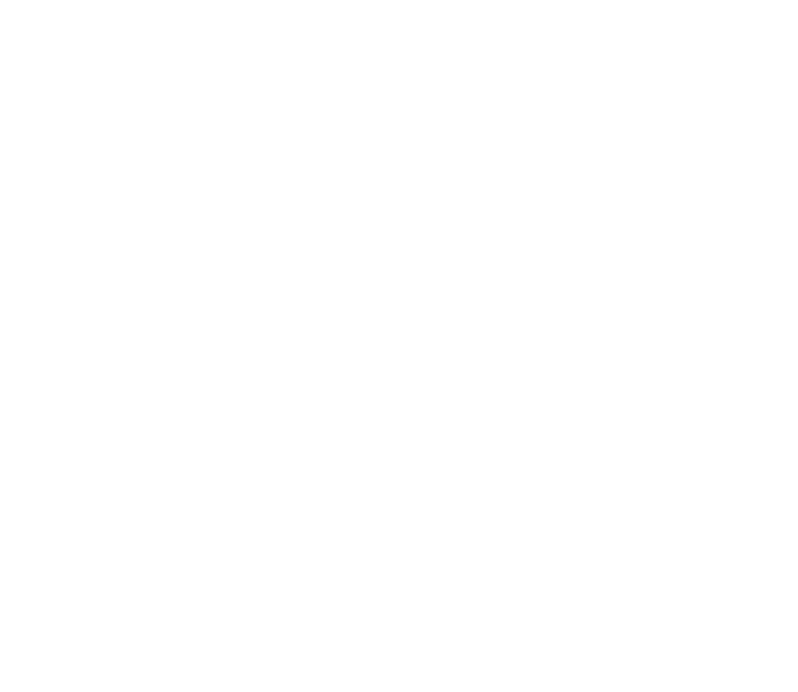
東京都荒川区・北区の
障害者就労移行支援事業所
アルファ日暮里駅前
アルファ王子
あなたらしく、安心して通える場所
私たちと、未来へ歩みましょう
利用者の皆さん及び見学・体験者の皆様、並びに事業所へ来所される関係各所の皆様へ
新型コロナウイルス感染症につきまして、厚生労働省の方針に従いアルファ日暮里駅前・王子では以下の対応と致します。ご理解とご協力をお願い致します。
※上記の対応に関しましては、今後の国や都からの要請により変更の可能性があります。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします
アルファ日暮里駅前・王子
精神、知的、発達、身体、難病

日暮里・王子各駅から徒歩1分の就労移行支援事業所アルファは、今のあなたにプラスアルファの自信をつけていただくためにサポートし、あなたの力を引き出します。
あなたらしく、安心して通える場所で就職を支援します。私達と一緒に未来へ歩んでいきましょう。
これからのあなたを、さらに素敵にするために。
アルファ王子
イベント
2024.04.8
アルファ王子
卒業生インタビュー
2024.04.8
アルファ王子
イベント
2024.02.28


一人ひとりに合わせた
丁寧なサポートプログラム
最長2年間の中で、スタッフと一緒に就労に向けた準備を進めます。
「資格を取りたい」「コミュニケーションに慣れたい」「就職のために自分には何が必要?」など、お一人おひとりに個別に対応するプログラムを作成し、就労を目指せます。一度お仕事を経験された方もいらっしゃれば、お仕事の経験がない方もいらっしゃいます。みなさんそれぞれの「こうしたい」「ここが不安」に寄り添います。


利用日数や利用時間は
希望のペースで
しばらく就労から遠ざかっていた方や外出が苦手な方もいらっしゃいます。
「まずは週3日から」「慣れるまでは午後だけ」など最初は無理のない範囲で通っていただき、徐々に通える日を増やしていきましょう。少しずつ体調のバランスや生活リズムを整えていきながら、就労を目指せます。


就職後の定着も
徹底してサポート
就労することが最終目標ではありません。企業への就労後もさまざまな不安や悩みを抱えることがあります。
「就労定着支援」は就労後も生じる生活面や職場での問題を解決し、障害者の方が安心して末永く働き続けられるようにサポートする福祉のサービスです。アルファを卒業したあとも就労先企業と連携をとり、みなさんが抱えるさまざまな悩みや不安を解消するためのサポートを行います。


Aさんは午後から週3回の通所が目標です。その為に体力増進プログラムのウォーキングは欠かさず参加しています。初めてのパソコン学習も自然と慣れてきました。
Bさんは2か月後のP検合格を目指して、学習しています。コミュニケーション力を高めるためにグループワークにも積極的に参加をしています。
Cさんは就労後の勤務に合わせ週5日の通所を継続しています。履歴書作成の為に自己PRの分析や希望する企業を調べ、本番の就職活動に向けて取り組んでいます。
「ホームページをみた」「たまたま通りかかった」アルファを知っていただくきっかけは様々です。
「どのような場所なのか?」「どのような訓練をしているのか?」「そもそも就労移行支援事業所ってどんなところ?」ぜひお問い合わせください。
「自分が利用対象に入るか分からない」「とりあえず話だけ聞きたい」という問合せも大歓迎です。
「実際にどのような場所でどんな訓練をおこなっているのか?」「雰囲気を確かめたい」など、ぜひともアルファ日暮里駅前・アルファ王子のアットホームな雰囲気をご覧になっていただきたいです。
スタッフが親切丁寧にご案内いたします。「不安だから、家族と一緒に見たい」という方も大歓迎です。
事業所の見学を経て、実際に通所し訓練を体験していただいております。
体験利用の日程はみなさん様々ですが、数日間体験をし、実際に「この事業所は自分と合うか?」確認することができます。
サービスを利用していただくには、お住まいの市区町村へ障害福祉サービス受給者証の申請を行う必要があります。
役所の手続きなど不安のある方は、スタッフが同行することも可能ですので心配いりません。
アルファを利用されるみなさんには個別のプログラムがあります。
一人ひとり相談しながら、一緒に今後の計画を立てていきます。就労に向けてどの様な訓練が必要なのか?あなただけのオリジナル訓練計画で、無理なく出来ることから始めましょう。
スタッフが寄り添い、サポートします。